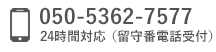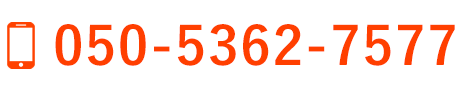コラム
技能実習生の受け入れと費用
外国人労務顧問技能実習採用特定技能昨今の労働力不足の状況鑑みて、海外からの技能実習生の受け入れを検討されている企業様も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
技能実習生にかかる費用は実習期間、就業中に関するものだけではありません。
実習生が渡航する前の費用の一部も受け入れ企業が負担することになります。また、各費用は「1人あたりにかかる費用」「初回のみの支払い」「年額」など、項目によって変動します。
そこで今回は技能実習生の受け入れに関してどれほどの費用がかかるかを解説します。
段階ごとに必要な金額を見ていきましょう。
1 監理団体への入会
技能実習生の受け入れは、どこかしらの監理団体を通して行われることが多いです。そこで、まずはどこかの監理団体となる協同組合への加入が必要になります。まず、この団体への入会金が1~10万円、出資金として1~10万円が必要となります。この金額は、団体によって大きく異なりますので、必ず確認しておく必要があります。
弊所から事業者様の諸条件に応じて、監理組合を個別に御紹介させていただくことも承っております。
2 受け入れのための事前訪問費用
技能実習生と面談して実際に人選を行うために必要な費用です。
航空券代や滞在費、食費などがこれにあたります。会社によってはいくらでも費用をかけられるところでもありますし、費用を削減したい会社にとっては、ここが考慮できる点でもあります。
弊所から監理組合様、事業者様の諸条件に応じて、現地国の送り出し機関を個別に御紹介させていただくことも承っております。
また、弊所が、事業者様の現地国での面談に同行させていただくことも承っております。
3 技能実習生の入国のために必要な費用
技能実習生として採用が確定すれば、ここから様々な費用が発生していきます。ざっくりいうと、日本に受け入れるための費用ということになります。
これら費用は、受け入れる実習生の母国やその人数、送り出し機関によって異なってきますが、基本的には多くが企業側の負担となります。
具体的には、渡航費用や申請書類作成・取次費用をはじめとして、その他にも、健康診断費用や講習費用(宿泊費、テキスト代)、講習手当(講習期間中の生活費)、パスポート取得費用、査証申請料、入管手続印紙税など、多くのものが考えられます。
4 技能実習生の入国後に必要な費用
技能実習生が入国した後にも費用がかかります。技能実習生は受け入れると、160~320時間(約1~2か月)にわたり、日本語研修などの法定研修を受けさせなければなりません。会社としてはこの講習費用と、実習生が講習を受けている間の生活費にあたる講習手当を出さなければなりません。
1~4 を合計すると、1人あたり65~75万円程度の費用がかかるとされています。実習を開始する前の段階でかなりの費用が必要になることがわかります。
5 就業開始後の費用
就業開始後の費用についてです。まずは、当たり前ですが、給与や社会保険料が必要となります。そしてそれ以外にも、監理団体に支払う監理費用がかかります。
以上のように、技能実習生の受け入れには金額的なコストがかなりかかることがわかりました。
また、金額的なコストではなく、組合を選定するための時間的なコストもかかります。
弊所・都総合法律事務所は、技能実習生の受け入れを検討されている事業者様に対して、技能実習生を受け入れるための仕組み作りを全面的に承っております。
「何もわからない」からで構いませんので、弊所・都総合法律事務所まで御連絡ください。
その他のコラム
東電、廃炉作業等に外国人労働者を受け入れ
人手不足外国人労務顧問特定技能廃炉作業が続く福島第一原発や再稼働を目指す柏崎刈羽原発などの現場での作業に外国人労働者を受け入れることを東電が明らかにしました。この外国人労働者は、特定技能の在留資格で受け入れられます。業務は、建設、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、自動車整備、ビルクリーニング、外食業が該当するとされていますが、主に建設に含まれる廃炉作業が中心となるようです。 法務省は、福島第一原発内で東電が発注する事業は、廃...
新型コロナウイルスと不法滞在
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問技能実習更新特定技能本コラムにおいても、新型コロナウイルスと外国人労働者への影響については、お伝えしてまいりましたが、先日、北海道でベトナム人の男性3人が、在留期限が過ぎているにもかかわらず、不法に滞在していたとして逮捕されたという事件が報道されました。 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200507/7000020865.html 新型コロナウイルスの影響で、本来来日する予定だった外国人労働...
ビザと在留資格のちがい
ビザ在留資格採用よく、「ビザ」、「労働ビザ」、「観光ビザ」とかの言葉を耳にしますが、 外国人労働者を海外から招へいするには、「ビザ」と「在留資格」の両方が必要となります。 むしろ「在留資格」の取得に注力される必要があります。 ただ、世間一般では、「ビザ」という用語のみが多用されていますが、特段、問題はありません。 在留資格が付与されればビザも、基本的に付与される関係にあるからです。 では、「在留資格」と「ビザ」は...
新型コロナウイルスの影響により解雇等された外国人の在留資格について
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問技能実習更新特定技能資格外活動許可新型コロナ感染症対策では、外国人の方にも大きな悪影響が及んでおります。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった外国人の在留資格の取り扱いについて、出入国在留管理庁より案内が出ています。今回はこの概要について紹介させていただきます。 解雇,雇い止め,自宅待機等となった方に係る対応(2020.4.30)(出入国在留管理庁) 現に有する在留資格の...
外国人による不動産売買の流れ
インバウンド不動産売買不動産投資外国人外国人が不動産を売買する場合 ①不動産仲介業者の選定 ②売買契約の締結 ③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し ④登記申請 ⑤新たな権利証の発行 というのが、主な流れになります。 ① 不動産仲介業者の選定 買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。 ② 売...