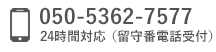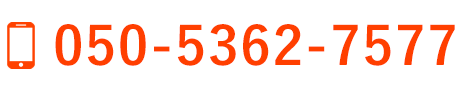コラム
新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について
ビザ不法就労入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国技能実習採用更新特定技能留学生資格外活動許可新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。
今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。
以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。
• タイ(7月29日(開始済み))
• ベトナム(7月29日(開始済み))
• マレーシア(9月8日(開始済み))
• カンボジア(9月8日(開始済み))
• ラオス(9月8日(開始済み))
• ミャンマー(9月8日(開始済み))
• 台湾(9月8日(開始済み))
以上の国や地域においては、往来を再開しているとは言ったものの、一律にすべての人が対称なわけではありません。
具体的には以下のようになっています。
(1)ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
(2)日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者。
(注:当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者、外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討します。)
詳細は各国の大使館等のHPを参照して下さい。
技能実習生をはじめ外国人労働者を雇用されている事業者様の大変さは、日常的に弊所も伺っております。
なにかお困りのことがございましたら
外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。
都総合法律事務所
弁護士 高谷滋樹
その他のコラム
建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)
人手不足外国人労務顧問外国人技能実習機構建設業技能実習2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...
増え続ける外国人労働者、多くの数値で過去最多
人手不足政策2019年4月12日の総務省の発表によると、2018年10月1日時点における外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が、過去最多の16万5千人となりました。 これは6年連続での外国人の社会増加であり、増加幅は年々大きくなっています。 増えた外国人の大部分は15~64歳であり、6年間で計64万人増えています。 中でも若い層の増加が顕著に確認できます。また、厚生労働省によると、2018年10月末時点での日本に...
医療滞在ビザとは?①
インバウンドビザ医療ツーリズム宿泊観光医療滞在ビザというものをご存じでしょうか。 最近、病院に行くと、外国人の患者を見かけることが増えたと感じる方もいるのではないでしょうか。 観光だけでなく、治療や手術を目的として日本に滞在する方もいます。 外国の方が日本の病院を受診する場合、「医療滞在ビザ」が発給されます。 このビザがあれば外国人は、日本で治療や検診、人間ドックなどを受けることができ、身の回りの世話をする同伴者を連れてくることも可能です。 ...
在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと
ビザ会社経営会社設立在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国渉外経営管理外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。 しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。 ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。 そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。 まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種...
技能実習の監理団体の許可
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。 この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。 監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。 一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な...